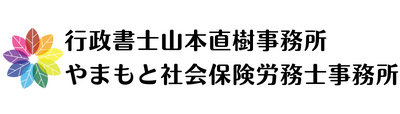ブログ
12.202021
「国際結婚した外国人の連れ子を日本へ呼ぶ」ビザはどうすればいいですか?

国際結婚で、外国人配偶者に子供がいる場合、その子供と日本で一緒に暮らしたいと思う方も多いのではないでしょうか?
この記事を読むと、外国人配偶者の子供を日本へ呼ぶためのビザ(在留資格)の要件について、お話しします。
国際結婚し、ビザ専門の行政書士として、ビザや国際結婚、離婚の悩みの相談を受けてきた私が、分かりやすく解説します。
外国人の連れ子を日本へ呼ぶためには?

国際結婚では、外国人配偶者は「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)で来日、その外国人に子供がいる場合は、子供を日本へ呼ぶことができるのでしょうか?
2つの事が考えられます
- 日本人と外国人配偶者の子供が養子縁組をして、その子供を「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)で日本へ呼ぶ。
- 定住者告示6号の「定住者」のビザ(在留資格)で日本へ呼ぶ。
日本人と外国人の子供が養子縁組すると、その子供は日本人の子供になり、「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)の取得が考えられます。
また、養子縁組は考えていないという方もいると思います。そのような場合は、2.の「定住者」のビザ(在留資格)を検討します。
今回は、養子縁組を希望していない方が、外国人配偶者の子供を「定住者」のビザ(在留資格)で呼ぶことを検討していきましょう。
「定住者」のビザで呼ぶにはどうすればいいですか?

「定住者告示6号」には、
「日本人の配偶者で「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)を持って在留するものの扶養を受けて生活する、未成年で、未婚の実子」
と規定されています。
まず、この規定を詳しく見ていきましょう。
- 未成年で未婚の実子
この規定は、子供が結婚している。成人であると該当しないので、この定住者の申請はできなくなってしまいます。 - 扶養を受けて生活する
一般に、義務教育までの年齢は問題がありませんが、15歳以上になると難しくなります。
また、高校卒業年齢(18歳)に達した子供は、独立の生計を営むことができると判断されやすくなります。
つまり、子供の年齢が高くなるにつれて、難しくなっていきます。
この、二つの要件に該当しなければ、許可の可能性は低くなります。
2022年4月1日から施行される「民法の一部を改正する法律」により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。同日以後は18歳以上の者は未成年に該当しなくなるので、注意が必要です。詳しくは出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。
次に、「扶養を受けて生活する」とは、入管では、どのように審査するのか、見ていきましょう。
なぜ、自分の子供と日本で、仲良く暮らしたいだけなのに、厳しく審査されるのか?

最近は「扶養を受けて生活する」という要件について、厳格に審査されています。
それは次のような理由が考えられます。
- 「定住者」は就業制限がないため、働くことを目的に日本へ来るのではないか。
- 日本語が話せないと、生活で障害になって犯罪に走る傾向があるから。
- 実際には日本に滞在しないで、本国で暮らして、来日できる権利だけを確保しようとする
申請には、このような、疑いが無いことを、説明することが、重要になってきます。
では、どのように、説明するのでしょうか。
- 現在までの扶養状況の説明
銀行の送金記録などを提出します。
親が日本にいる間は、本国で子供の面倒を誰が見ていたのか、どうして、日本へ子供を連れて来なければならないのか、その理由を具体的に説明する必要があります。 - 子供が来日してから、どのように扶養していくか。
経済的なこと、子を受け入れる学校との打合せ状況、今後の教区計画、住まいが子供と一緒に暮らせる、広さが十分あるかなどを具体的に説明する必要があります。
このようなことを、証明できる「資料」や「理由書」で入管へ説明する必要があります。
まとめ:外国人の連れ子は、日本へ呼ぶことができる。
今回は、外国人の連れ子を「定住者」というビザ(在留資格)で日本へ呼ぶ要件をお話ししました。ポイントをまとめると次の通りです。
- 連れ子と日本人が養子縁組しなくても「定住者」というビザ(在留資格)で呼ぶことができる。
- 子供が、「成人に達している」、「結婚している」と、「定住者」ビザ(在留資格)で呼ぶことが、かなり難しい。
- 子供の年齢が高くなれば、なるほど、呼ぶことが難しくなる。
- 「扶養を受けて生活する」の要件は厳格に審査されている。
親として、自分の子供と日本で暮らしたいと思うのは普通のことです。
そのためにはビザ(在留資格)が必要になり。そのビザは厳格に審査される。
もしかしたら一緒に暮らせないのでは?と不安になります。
また、子供が来日してから、将来どうするのか?ビザ(在留資格)についても考えていくことも必要になってきます。
そのような、不安をなくすためにも、ビザ(在留資格)の専門家である行政書士にご相談ください。
まずは、お問い合せページからご連絡ください。こちらから、ご希望の方法でご連絡差し上げます。